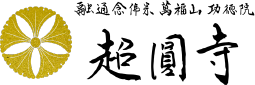超圓寺の納骨・永代供養
舎利殿(納骨堂) ~本堂の奥~
舎利(しゃり)とはお骨のこと、とくに喉仏のお姿になられた魂=菩提(ぼだい)を納める場所です。本堂の奥、もっとも静まるところに安置いたしております。
そして菩提を納める寺、すなわち“菩提寺”…超圓寺は納骨・結縁くださる皆様の菩提寺です。
本骨(喉仏)納めのほかに、永代供養(※永代…50年にわたって、先祖代々となるまでの供養)は特別の黒漆塗りの供養壇にお預かりしております。舎利殿のご本尊は平安時代の古い阿弥陀三尊仏です。廃寺となり幻となった“結崎寺”の伝統をひくものかもしれません。
夢想殿(永代納骨堂) ~新舎利殿~
本堂右の玄関奥に、永代納骨堂「夢想殿(むそうでん)」が新たに落成しました。
舎利殿と同様、大切な故人様のお舎利(お骨)をお祀りして、永代供養いたします。
夢想殿のご本尊には観音様をお迎えしております。
結の御廟(永代供養納骨)
~本堂お内陣のなか~
結の御廟(ゆいのごびょう)は本堂内にまつられる永代納骨です。
「俱会一処(くえいっしょ)」…あの世で再会できる喜びを分かち合い、納められるお骨は阿弥陀如来のお姿となってこの世を照らしてくださいます。
無数の阿弥陀如来は、結縁くださる皆様の思い…お念仏の数ほどに切なさや悲しみを幸せに変えてくださいます。このご縁を永代に結び静まる厳かな霊廟です。故人様の芳名を刻んでまつりますので、納骨後いつでもお参りください。
まほろばの碑(永代供養合祀墓)
~境内、山門の脇~
先祖代々のお墓や、深い絆に結ばれた夫婦でともにお墓に眠りたい…
そんな本心を隠して、現代の生活スタイルのなかでは「お墓」をもつ望みを諦めざるをえない方が多くなって参りました。我々は一度しかない人生“一生”を懸命に生きて、亡くなります。どれほど尊い一生も、時間とともに忘れられていきます。
しかしこの世に生きた“思い”は、故人とご縁や関わりを持ったすべての方々の心に、必ず引き継がれています。その尊い“思い”を安め静めるべく、超圓寺では合祀墓『まほろばの碑』を発願し建立いたしました。
先立たれた故人と向き合い、静かに手を合せる。伝えたいことができたなら、ここに参る。
『まほろばの碑』の前に立てば、自分自身もまた脈々と受け継がれて来た尊い命であるとあらためて感じられることでしょう。ここが感謝と励ましを受けるみな様の“心のまほろば”になることを信じ願ってやみません。
位牌堂 ~本堂の左のお堂~
世代とともに古くなったご先祖様のお位牌や、供養されなくなったお位牌を納める永代供養堂です。
供養が滞ってしまわれたご先祖様も浮かばれます。我々ひとりがこの世に生まれるためには、両親・祖父母だけでなく、顔も名前も知らないご先祖様方が一生懸命に生きて、子を生み育ててくださったお陰なのですね。
供養料・お布施について
永代供養
| 納骨壇 (舎利殿・新舎利殿) |
結の御廟 |
|---|---|
| 50万円 | 10万円 |
| まほろばの碑 | 位牌堂 |
| 5万円 | 10万円 |
※まほろばの碑について、故人のお名前を刻む芳名板は別途2万2千円必要です。
ご不安や心配ごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
その他の納骨
| 本骨納め | 保管納骨(一時預かり) |
|---|---|
| 5万円 | 1万2千円(年間) |
- 本骨納め
- いわゆる永代供養(供養をお寺にお任せしてしまう)ではありませんので、お正月・お彼岸・お盆などには、お寺にお参りに来ていただけるのが前提です。
- 保管納骨(一時預かり)
- お墓がまだできていない、永代供養するか迷っている等々の理由で、お骨を長く手元に置いてある場合があります。悲しみのなかと存じますが、執着の苦しみから離れるべく、敢えてお身体のお骨を手放すことが、昔からの知恵です。
保管させていただくお骨は、お寺の納骨堂に仮安置してお祀りいたします。
故人様の月命日の回向・供花代(1千円)12ヵ月分としてお納めください。
ご相談の流れ
- 1
-
お問い合わせ
お電話(0745-44-0555)または、問い合わせフォームからお問い合わせください。
見学希望日や納骨希望日をお伺いいたします。
- 2
-
見学・ご契約
お申込み書をお書きいただき、ご契約となります。
ご契約と同時に納骨いただいても結構です。※遠方の場合など、必ずしも見学をする必要はございません。
- 3
-
納骨
本堂で読経の上、納骨施設へ安置いたします。

必要なもの

- 遺骨

- お布施

- 火・埋葬許可証
もしくは改装許可証

- 認印

- 身分証明書
※火・埋葬許可証(改装許可証)の申請者に記載されている方と、納骨のお申込者が異なる場合は、
故人様との関係を証明する書類をお持ちください。(住民票の写し、戸籍謄本など)
(必須ではありません)